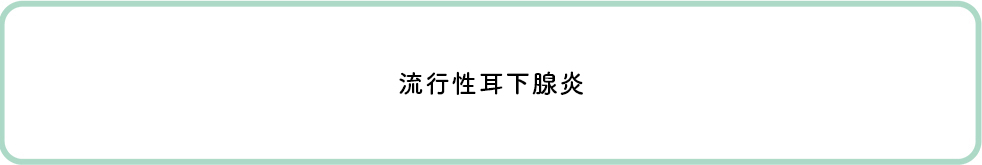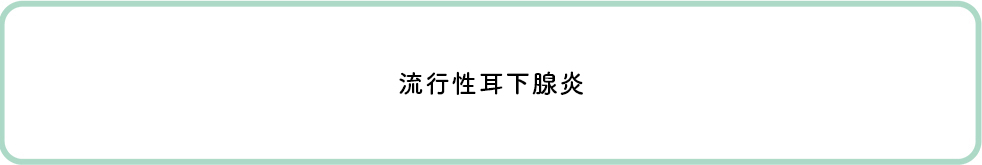
ムンプスウイルスによる感染症で、一般には「おたふく風邪」として知られています。3歳から6歳の小児に多く見られる感染症です。
2、3週間程度の潜伏期間ののち、突然の発熱、片側の耳の下、あるいは両側の耳の下の腫れと痛みが起こります。2、3日以内には両側とも腫れ、顎の下まで広がることがありますが、通常1、2週間で症状はおさまります。また、感染しても30%程度の方は、症状が現れないとされています。
感染した人の唾液やくしゃみなどの飛沫を直接吸い込むことで感染する飛沫感染と、飛沫が付着した手で鼻や口を触ることで感染する接触感染が原因で感染が広がります。
感染力が非常に高い感染症ですが、予防接種により、強力に感染を防止できます。しかし、感染後においては、特効薬と呼べる物はありません。
小さなこどもの場合、幼稚園や保育園などの集団生活に入る前に、ワクチンによって予防しておく事が、最も有効な感染予防法です。現在、任意予防接種として1歳以上で接種することができます。
成人が感染した場合、症状が重くなる傾向があります。重症化すると、髄膜炎や精巣炎、難聴などの合併を引き起こす可能性があるので、おたふくかぜを疑うような症状が見られたときは、1度病院を受診しましょう。
特に1週間以上熱が下がらない場合や、ひどい頭痛や嘔吐を伴う場合はすぐに病院を受診してください。特別な治療法は無く、症状に応じた対症療法が基本となります。発熱などに対してはお熱を下げるお薬の投与を行います。また、脱水症状を防ぐため、こまめな水分補給を心がけることが大切です。
次のような症状にお悩みの方はご相談ください。
症状に関する関連用語も記載しております。
(クリックで内容が表示されます)
症状として、
頬が腫れる、耳の下が腫れる、耳の下が痛い、発熱がある、食べ物を噛むと痛い、飲み込むと痛い、倦怠感がある、頭痛がする、喉が痛い、顔が腫れる、首が腫れる、顎が腫れる、耳周りが痛い、体がだるい、食欲がない、寒気がする、悪寒がする、筋肉痛がある、
が出るなどがあります。
症状に関する関連用語として、
おたふく風邪の症状、流行性耳下腺炎、唾液腺炎、精巣炎、卵巣炎、無菌性髄膜炎、難聴、耳の違和感、発熱、痛みを和らげる治療、対症療法、安静、水分補給、解熱鎮痛剤、感染予防、飛沫感染、マスク着用、ワクチン接種、予防接種、流行時期、感染拡大防止、登園停止
等があります。