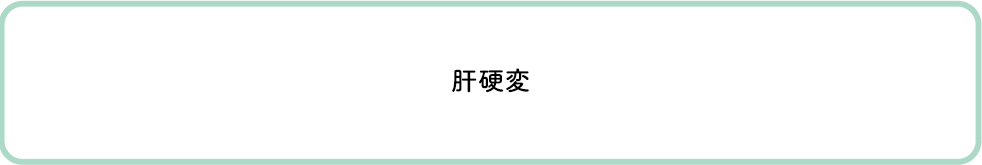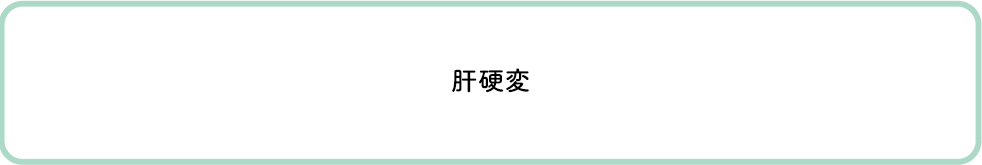
病態概論
肝硬変とはウイルスやアルコールなどにより肝臓に炎症が生じ、肝臓が硬くなっていく病気のことです。
自覚症状はなく、長い年月をかけて肝炎の状態から最終的に肝硬変になっていきます。それに伴い肝臓の働きが低下します。
症状
肝臓は「沈黙の臓器」と言われ、初期の段階では、肝障害が出ていても自覚症状はほとんどありません。そのため発見が遅れることがよくあります。
肝硬変は長期間症状のない時期を経て、症状を現すようになります。症状が出てしまうと、お腹に水が溜まる腹水(ふくすい)・皮膚や目が黄色くなる黄疸(おうだん)・食道や胃の静脈が膨らんでその部分が破れてしまう食道・胃静脈瘤破裂(しょくどう・いじょうみゃくりゅうはれつ)が起こることがあります。
原因
肝硬変は血液感染と生活習慣の大きく2つに原因が分けられます。血液感染は主に血液・体液を介してウイルス感染するB型・C型肝炎などがあげられます。
これらの感染により慢性肝炎へ発展し、長期間続くと肝硬変となります。ウイルス性の肝硬変は高頻度で肝細胞がんを引き起こす原因となります。
生活習慣によるものとして、お酒によるものが原因として多いです。長年にわたる飲酒が肝臓を傷つけ肝硬変へ至ります。
また、アルコールを飲まない人でも、肥満や糖尿病・高血圧が原因となる場合もあります。
診断
今まで一度も肝炎検査を受けたことがない・検診で肝機能異常を指摘された・30年以上前までに輸血や大手術を受けたことがある方は、いちど検査を受けてみましょう。
早期に診断して治療することで、肝硬変・肝がんへの進展を防ぐだけでなく、高い確率で合併するといわれている肝細胞がんを未然に防ぐことが望まれます。
治療
肝硬変を根本的に治す薬は現時点では存在しません。そのため、症状に応じた対症療法が基本となります。ウイルス性肝硬変の場合は抗ウイルス薬を服用します。
アルコール性肝硬変の場合は、アルコールを控える・運動・食事制限が望まれます。
予防
早期発見・早期治療が大切になります。まずはお酒を飲む量を減らす、生活習慣病に気を付けることで予防できます。
またB型・C型肝炎のように血液・体液を介して肝硬変になることもありますので、常識的な社会生活を心がけ危険な行為を行わないようにしましょう。B型肝炎ウイルスに関してはワクチン接種をすることで予防が可能です。
また、肝機能は健康診断で簡単に分かります。定期的に受診して健康状態をチェックするようにしましょう。